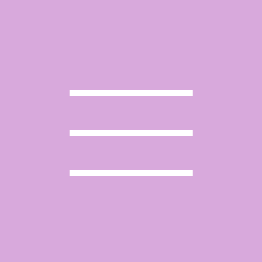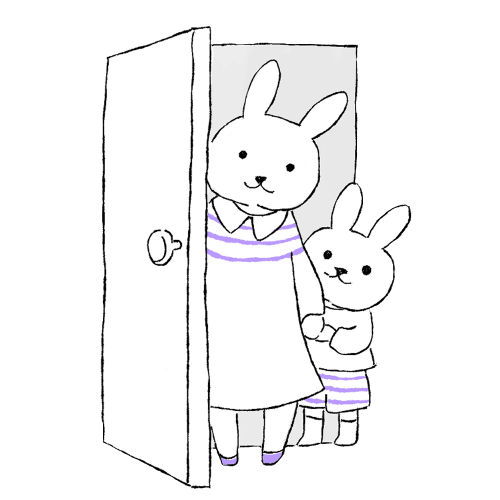自己紹介
2025年8月10日 教室関連
どうやら日本が経済成長をはじめた1950年代、東京都葛飾区に生まれました。
3歳でバレエスクールに入門志願しましたが、踊っている子供たちの中に一人で入っていく勇気が出せないまま時が経過し、最初の習い事に挫折しました。
今、新しい生徒さまに出会うとき、この日の私を思い出し、やり始めの最初の一歩のキッカケをなんとか上手く作ってあげたいな、と心から思います。
6歳になって、次に選んだのがピアノ教室です。
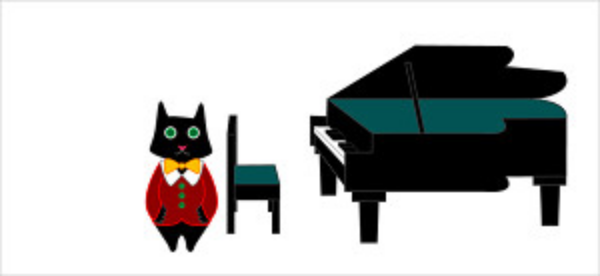
レッスンが先生と1対1だった為か、今度はすんなり溶け込めました。
この時の最初の教本が、田中澄子著「色おんぷ」です。
私に音の色彩感を作ってくれた素晴らしい教材との出会いだったのですが、その時の私は音符に色を塗るのが子供っぽくて、恥ずかしくてイヤだったのでした。
教材やレッスン内容は、それを学ぶことによって得られる力や狙う学習効果を十分説明して、生徒さまがプライドを持って練習に取り組めるようにすることが必要だと痛感します。
それとともに、生徒さまが自分の思いを話しやすい雰囲気を作ることが、なによりも大切ですね。
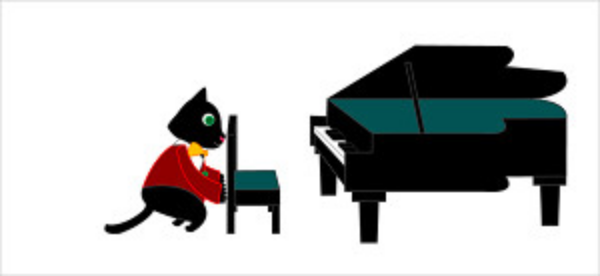
みんながのんびりしているピアノ教室だったので、ことさら怠けている意識もなしに、ほとんど練習しないで小学校時代を過ごしました。
でもピアノはすきで、音楽はいつも私と一緒にありました。
例えば、レッスン通いに前を通る「すみれ幼稚園」。
陽当たりの良い園庭を眺めると、ストリーボックの「すみれ」が口をついて出るのです。
友達と遊んだ原っぱでクローバーを摘みながら見上げる晴れた空は、まさにベアーの「5月に」でした。
ウェーバーの「人魚のうた」は、ピーターパンの絵本のイメージぴったりで、今も忘れません。
こんな風に遊んで過ごす中で育った「ピアノが好きだ」という気持ちが、生涯の友として長くピアノを続けて行ける「心の核」になっていったのだと思います。
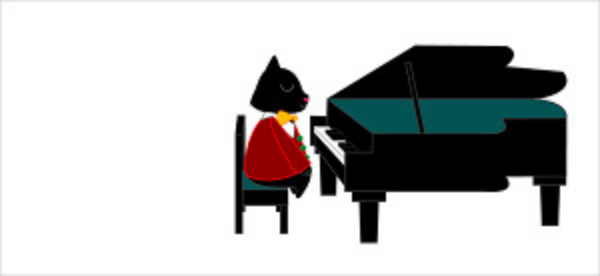
ファッションとカッコ良さを気にする10代、白百合学園中学校に入学すると、学校の友人たちは皆ピアノが上手で、私のピアノなどファッションにもならないことを知りました。
ショックでした!
私は今、生徒さまたちがこんなショックを受けないように、検定やコンクールなどをお薦めしているのです。
気持ちを切り変えて、その頃テレビ出演などで活躍中だった、上野学園大学講師・千田千恵先生の生徒になりました。先生の華やかなキャリアと、ピアノという楽器の表現力にたちまち魅了されて、音楽進学を決意します。
高校時代は、東京音大学部長・武沢武先生に、夕方6時を過ぎるとウイスキーグラス片手という破天荒な、でも内容の濃いレッスンを受けました。
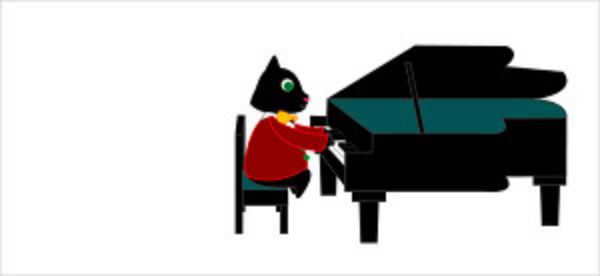
そして、上野学園大学ピアノ科に入学。
萩原和子教授(日本ピアノ教育連盟副会長)のもとで、先生の大声と地団太とともに、専門的なクラシック音楽の捉え方を仕込まれます。
一方、山田流筝曲教授・藤井喜恵井氏に入門し、大学卒業までの3年間で「中許」を得ました。
日仏学院のフランス語コースに週4日も通ってみたり、自分の進路に悩み、模索する大学の4年間でした。
卒業後は楽器店や自宅でピアノを教えたり、リトミックの伴奏をしながら、声楽家 江川きぬ先生(日墺文化協会理事)の練習ピアノを弾きました。
この伴奏の仕事を通して、往年の声楽家 佐々木成子氏のレッスンや、ドイツ人ピアニスト ヘルムート・ドイチ氏、芸大講師・岩津章子氏(後に1年半ほど師事する)などの演奏に接し、私自身も多くのコンサート演奏のチャンスに恵まれました。
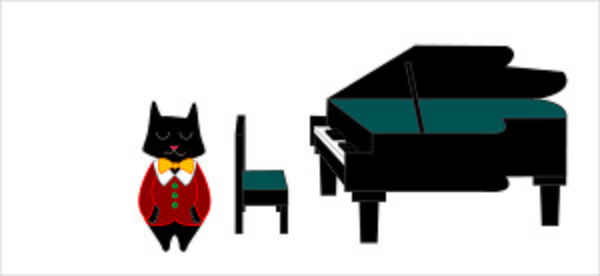
更なるラッキーチャンスは、1978年に訪れます。3ヶ月間、ヨーロッパ遊学の旅に出たのです。
この放浪の旅が、私のピアノ観を変えました。教会で行われる素朴なコンサートや、街角に立つストリートミュージシャンの演奏に心を洗われて、スランプを脱し、純粋に自己燃焼をめざすピアノを弾こうと心が決まります。
帰国後、新たな師、中河幸先生(武蔵野音大教授)に師事して、コンサート活動を再開しました。学生時代にも増して、練習に没頭したピアノ三昧の日々を約4年間、結婚、出産まで続けました。
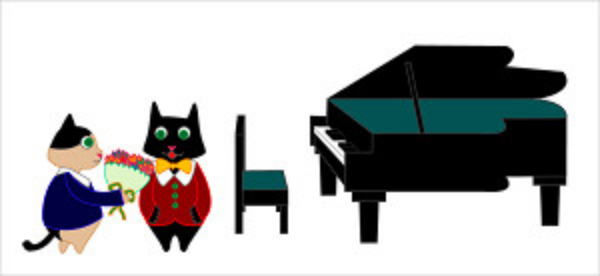
出産後、指導法を研究するためにわが子3人をそれぞれ違う音楽教室に通わせました。
気楽なところは力が付かず、実力は付いても山のように課題がでるところは、苦いだけで、楽しさとは程遠いものでした。3人とも私ほどは、ピアノが好きになりませんでした。
実力をつけることと、ピアノが好きになることを両立させることの大切さ、難しさに悩み、生徒さま一人ひとりに違う教則本を使って教材を比較検討したり、さまざまな指導講座に通ったりしました。
そこで出会ったのが、バスティーンメソッドと藤原亜津子先生(全日本ピアノ指導者協会理事)です。先生の講座に感激して書いた手紙が、「感動の質問」として、指導者協会のサイトに掲載され、その後約2年間、先生の生徒指導を継続的に見学できることになりました。
まさに「目から鱗」!「少しの苦労でほんものの実力をつけること」が可能なことを知りました。しかも、楽しむ要素もふんだんに取り入れて!
苦労を感じていたピアノ指導が、もう楽しくて楽しくて、生徒さまが毎週レッスンにくるのが、待ち遠しいようになって来ました。
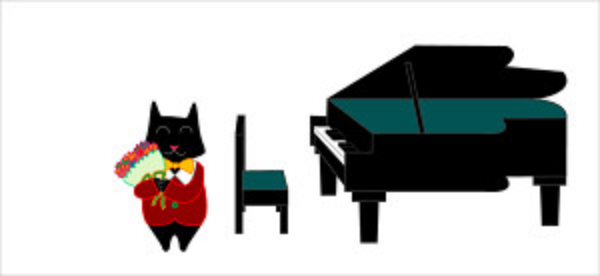
そこから、ドラマチックに物事が展開し始めました。
2001年には、アメリカ・サンディエゴに出かけて、メソッドの創始者、ジェーン・バスティン先生から直接指導を受けることが出来ました。
2002年には指導者協会主催のテレビ番組に生徒3人が出演し、またこの年、雑誌インターナショナルDA-i-JOBに「仕事の国際化」というテーマで、写真入りで教室紹介の記事が載りました。
2003年に松戸市に転居しました。
これをきっかけに、指導のメンタル面強化のため、慶応義塾大学文学部哲学科に学士入学し、心理学を学びはじめました。
コンクールに入賞する生徒さまも多くなり、関東大会全国大会へと進む人も出てきました。
また一方、中学、高校、大学と忙しくなっても退会しないで、レッスンの時だけのピアノを楽しんで続けてくださる生徒さまも増えたように思います。
私自身も子育てが終わりかけ、演奏活動を再開しました。
ウィーン国立アカデミー講師・木暮淳子先生、フランス国営放送ピアニスト・永富和子先生のご指導を受け、恵比寿ガーデンプレイス、東京文化会館などで、年に数回リサイタルやジョイントコンサートを行っています。
その他、複数のピアノサークルで、色々なホール、様々なメーカーのピアノを弾くことも楽しんでいます。
これからは、私自身が生涯の友としてピアノを楽しみながら、生徒さまにも、それぞれの個性に合った、また、その時々の状況に合ったピアノとの付き合い方を提案しつつ、ともに生き生き楽しいレッスンライフを展開して行きたいと願っています。
私と一緒に、是非ピアノを楽しんでみませんか!